賃貸物件に住んでいると、避けて通れない「トラブル」。
「こんなとき、どうすればいいの?」と悩んでしまう場面も少なくありません。
今回は、賃貸でよくあるトラブルの例と、その正しい対処法をわかりやすく徹底解説!
これを読めば、いざというときに慌てず冷静に対応できます。
1. よくある賃貸トラブルとその原因

隣人トラブル(騒音・マナー違反など)
賃貸生活で最も多いトラブルの一つが隣人トラブルです。特に多いのは、深夜のテレビや音楽の音、足音、ペットの鳴き声などによる騒音問題です。
また、共用部(廊下やエントランス)に私物を置く、ゴミ出しルールを守らないなど、マナー違反が原因となることも少なくありません。
【防止策】
- 内見時に壁の厚さや周辺住人の生活音をチェック
- 賃貸契約前に「住人層(ファミリー層が多いか、単身者が多いか)」を不動産会社に確認
- 騒音トラブルが発生した場合は、直接注意せず、必ず管理会社を通して対応する(個人間でのトラブル悪化を防ぐため)
設備の故障(エアコン、水道、給湯器など)
住み始めてから発覚するトラブルの代表例が、設備の故障です。
特に多いのは、エアコンの冷暖房不良、水漏れ、給湯器の故障など。生活に直結する設備のトラブルは、放置すると健康被害や大きな修理費用問題にもつながります。
【防止策】
- 入居前にエアコン・水道・シャワーなどの動作確認をする
- 設備不良を見つけたら、すぐに写真を撮り、管理会社またはオーナーに正式に連絡
- 契約書に「設備故障時の修理負担者(貸主か借主か)」が明記されているか確認しておく
敷金の返還トラブル
退去時に必ず発生する可能性があるのが、敷金返還に関するトラブルです。
本来、敷金は原状回復費用を差し引いた上で返還されるべきですが、過剰なクリーニング費用や修繕費を請求されるケースもあります。
【防止策】
- 入居時に室内のキズ・汚れを写真で記録しておき、管理会社に報告
- 国土交通省の「原状回復ガイドライン」に目を通し、適正な負担範囲を理解しておく
- 退去立ち会いの際に、請求内容に疑問がある場合はその場でサインしない
契約内容の誤解(原状回復義務など)
賃貸契約には、借主側に課される「原状回復義務」があります。
しかし、「原状回復」の範囲について誤解していると、不要な費用負担やトラブルに発展するリスクがあります。
【防止策】
- 契約書の「原状回復義務」条項を必ず確認
- 「通常損耗」(経年劣化や自然消耗)は借主負担ではない、という原則を理解する
- 壁紙や床に傷をつけた場合は、早めに管理会社に相談することで対応がスムーズになる
大家・管理会社とのコミュニケーション不足
設備故障や更新手続きなど、入居中には必ず大家さんや管理会社とのやり取りが発生します。
この時、連絡ミスや意思疎通不足がトラブルの原因になることも。
【防止策】
- 重要な連絡は電話だけでなく、必ずメールや書面で記録を残す
- 管理会社の営業時間・緊急連絡先を事前に把握しておく
- 対応に不満がある場合も、冷静かつ丁寧なやり取りを心がける(感情的になると余計に解決が難しくなる)
このように、賃貸生活ではさまざまなトラブルリスクがありますが、事前の確認と冷静な対処を心がけることで、多くの問題は防ぐことができます!
2. トラブル別・正しい対処法

トラブルが起きたとき、焦って自己判断で動いてしまうと、かえって状況が悪化することもあります。
ここでは、よくあるトラブル別に正しい対処法を具体的に解説します。
● 隣人の騒音がひどい場合
▶ まずは冷静に記録を取り、管理会社に相談するのが鉄則です。
- 【ステップ1】
騒音が気になる日時、内容(例:夜中1時〜3時、重低音の音楽、ドアの開閉音など)をメモに残す。可能ならスマホで音声記録も。 - 【ステップ2】
ある程度データが揃ったら、管理会社や大家に正式に相談しましょう。記録があれば、客観的に訴えやすくなります。 - 【注意点】
絶対に直接クレームを言いに行かないこと。
個人同士の対立になり、トラブルが激化するリスクが高まります。
必ず第三者(管理会社)を介して対応を依頼しましょう。
● 設備が壊れた!
▶ 原因が「経年劣化」か「借主の故意・過失」かで、対応が分かれます。
【経年劣化の場合】
長年使用した結果の故障(例:エアコンのガス抜け、水道管の劣化)などは大家(貸主)の負担で修理されるのが原則です。
すぐに管理会社または大家に連絡し、状況を伝えましょう。写真や動画を撮っておくとスムーズです。
【借主の故意・過失の場合】
例えば、重いものをぶつけて壁に穴を開けた、水をこぼしてフローリングを傷めた、などの場合は借主の負担となることが一般的です。
修理費の見積もりを提示される前に、どちらの責任かの話し合いをしっかり行いましょう。
POINT契約書に「設備故障時の対応ルール(誰が負担するか)」が明記されている場合もあるので、事前に内容を確認しておくと安心です。
● 敷金が返ってこない
▶ 国土交通省の「原状回復ガイドライン」をもとに交渉しましょう。
- ステップ1
敷金返還に関するトラブルが起きた場合、まずは契約書を確認。さらに、国交省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、適正な負担範囲を把握します。 - ステップ2
ガイドラインに反する過剰請求(例:通常使用による壁紙の色あせに対する請求など)をされた場合は、冷静に管理会社や大家に説明・交渉しましょう。 - ステップ3
話し合いで解決できない場合は、内容証明郵便を利用して正式な返金請求書を送付する方法もあります。
さらに必要であれば、簡易裁判所での少額訴訟(請求金額60万円以下)を検討するのも一つの手です。
POINT退去時に室内の写真を撮っておく、立ち会い時の説明を録音しておくと、万一のトラブル時に有利な証拠になります。
トラブルが起きたときに大切なのは、
- 感情的にならず、
- 客観的な記録を残し、
- ルールやガイドラインに基づいて、
- 冷静かつ適切な手続きを踏むこと。
早めの対応と、第三者(管理会社・国のガイドライン)をうまく活用することで、無駄なストレスや損失を防ぐことができます!
3. トラブルを未然に防ぐためにできること

賃貸生活でトラブルを完全にゼロにすることは難しいですが、事前の対策次第で大半の問題は未然に防ぐことが可能です。
ここでは、入居前後にできる具体的な対策を紹介します。
契約前に細かく内容を確認(重要事項説明をスルーしない!)
▶ 賃貸契約時には、不動産会社から「重要事項説明書(重説)」が交付されますが、これを流し聞きしたり、早く終わらせようとせず、しっかり内容を確認することが大切です。
確認すべき主なポイント
- 家賃・管理費・更新料などの支払い条件
- 原状回復義務(退去時の修繕負担の範囲)
- 設備の故障時の修理負担(貸主・借主どちら負担か)
- ペット飼育・楽器演奏・DIYの可否
- 特約条項(例:退去時クリーニング費用の負担など)
疑問点があれば、その場で必ず質問し、口頭ではなく書面に記載してもらうことが重要です。
後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、契約内容を完全に把握してからサインしましょう。
入居時の状態を写真で記録しておく
▶ 入居直後の室内の状態は、必ず写真に残しておくことがトラブル防止に役立ちます。
【撮影すべきポイント】
- 壁、床、天井のキズ・汚れ
- 水回り(キッチン、トイレ、浴室)のカビやサビ、ひび割れ
- 扉、窓、建具の破損・不具合
- エアコンや給湯器など設備の外観
【ポイント】
撮影日時がわかるように、スマホの「撮影日記録」機能をオンにして保存しましょう。
管理会社に「この部分、最初からこうでした」と報告しておくと、退去時の原状回復費用をめぐるトラブルを防ぐ効果もあります。
些細なことでも管理会社に相談しておく
▶ 住んでいるうちに気になることが出てきたら、「まあいっか」と放置せず、早めに管理会社に相談するのが鉄則です。
【相談例】
- エアコンの効きが悪い
- 共用部にゴミが放置されている
- 夜間の騒音が気になる
- 水道の蛇口からポタポタ水漏れしている
些細なことでも記録として残しておけば、後から大きな問題になったときに「以前から相談していた」と主張しやすくなります。
特に設備系の不具合は、早期発見・早期対応が肝心です!
近隣との挨拶をして、関係を築いておくのも意外と大事
▶ 入居時に両隣と上下階に簡単な挨拶をしておくと、いざという時に助け合える関係を築きやすくなります。
【挨拶のメリット】
- 騒音や生活音の許容範囲を広げてもらいやすくなる
- トラブルが発生した時に直接話しやすくなる
- 防犯・災害時に助け合える安心感が生まれる
【挨拶のポイント】
- 簡単な手土産(500〜1000円程度のお菓子やタオルなど)があると丁寧な印象に
- 「○○号室に引っ越してきました○○です。今後ともよろしくお願いします」程度の簡単な挨拶でOK
あくまで軽いご挨拶で構いませんが、顔を知ってもらうだけでもトラブル防止に効果絶大です!
契約前、入居直後、生活中の小さな行動を意識することで、
トラブルの発生率をぐっと下げ、万一のときも自分を守る材料を確保できるようになります。
「後から後悔しないために、最初に丁寧に確認・記録・相談を!」
この意識を持つだけで、賃貸生活の安心感が大きく変わります!
4. どうしても解決しないときは?相談先一覧

どれだけ気をつけていても、自分だけでは解決できない賃貸トラブルに直面することもあります。
そんなときは、一人で抱え込まず、専門の相談窓口を頼ることが大切です。
ここでは、トラブルの種類や状況に応じて利用できる相談先を紹介します。
消費生活センター
▶ 賃貸住宅に関する契約トラブル、敷金返還、原状回復費用などの問題について、無料で相談できる公的機関です。
- 【相談できること】
- 敷金が不当に返還されない
- 契約条件と違う説明を受けた
- 高額な修繕費用を請求された など
- 【ポイント】
地元の消費生活センターに連絡すると、専門相談員が対応してくれます。
必要に応じて、業者との交渉支援や、弁護士相談への橋渡しもしてくれることがあります。 - 【調べ方】
「◯◯市 消費生活センター」で検索、または国民生活センターのサイトからも地域別に検索可能。
弁護士会の無料相談窓口
▶ トラブルが深刻化し、法的な知識や対策が必要になった場合は、各地の弁護士会が実施する無料法律相談を活用しましょう。
- 【相談できること】
- 敷金返還請求の方法
- 内容証明郵便の作成アドバイス
- 賃貸契約解除や損害賠償請求に関する相談
- 【ポイント】
無料相談は時間制限(30分程度)があるため、事前に相談内容を整理しておくとスムーズです。
初回無料で、その後正式に依頼する場合の費用説明も受けられます。 - 【調べ方】
「◯◯県 弁護士会 無料相談」などで検索すると、地元の弁護士会の相談窓口情報が見つかります。
賃貸住宅紛争防止条例のある自治体窓口
▶ 地域によっては、賃貸トラブルを防止・解決するために**「賃貸住宅紛争防止条例(通称:紛争防止条例)」**が制定されています。
- 【条例がある主な地域】
- 東京都(賃貸住宅紛争防止条例)
- 大阪府など
- 【相談できること】
- 賃貸契約前後のトラブル相談
- 原状回復義務の範囲についての疑問
- 退去時の敷金精算についての指導
- 【ポイント】
専門相談員や行政書士、弁護士などが無料相談を受け付けていることもあります。
地元自治体の公式サイトから対象窓口をチェックしましょう。
国民生活センター(電話:188)
▶ どこに相談したらいいかわからない場合や、最寄りの相談窓口を知りたい場合は、国民生活センターの「188(いやや)」番に電話するのが最も手軽です。
- 【相談できること】
消費者トラブル全般(賃貸住宅トラブルも含む) - 【使い方】
電話をかけると、住所地に最も近い消費生活センターや専門窓口に案内してくれます。 - 【ポイント】
188は土日祝も対応している自治体が多いため、平日忙しい人でも利用しやすいです。
5. まとめ:賃貸トラブルは「知って備える」がいちばんの対策
トラブルは「起きてから」では遅いことも。
しかし、正しい知識と対応策を知っておけば、大きな問題に発展する前に防ぐことができます。
「備えあれば憂いなし」。
安心・快適な賃貸ライフのために、今のうちからできる対策をしておきましょう!







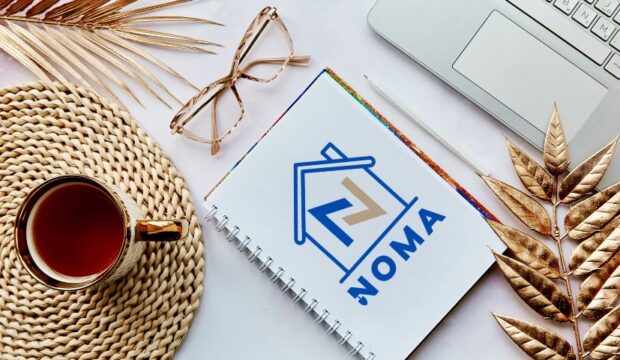


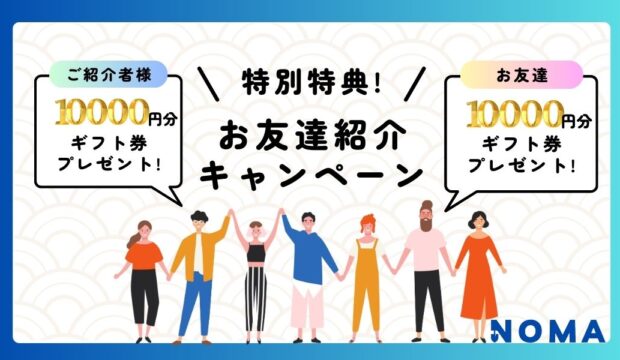

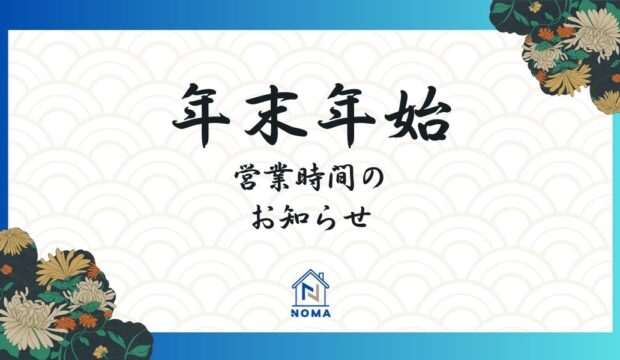
























コメント